令和元年10月より新しくはじまった子育て支援制度「幼児教育・保育の無償化」
月々の保育料の負担額が大きく減ったという声もある一方で、
「今まで不要だった給食費が実費になり、支払いが上がった…」
こんなケースが見受けられています。
また、ひとり親家庭の中では、今回の制度を受け「子供の保育にかかる負担額が増加した」という声もあがっています。
少子化対策と子どもの未来のために定められた保育料無償化制度なのに、なぜこのようなことが起きているのでしょうか?
- 幼児教育無償化で給食費が上がる人は?
- 給食費の免除対象は?
- 結局、給食費はいくらになるの?
今回は以上のポイントを中心に、幼児教育・保育の無償化について紹介していきたいと思います。
保育園無償化で給食費が上がる理由

「保育の無償化」と聞くと、保育にかかる全ての費用が無料になるかのように受け取ってしまいがちですよね。
しかし、注意しておきたいのが、今回の新制度で無償化の対象となるのは「保育施設の利用料」だということです。
幼稚園・保育所・認定こども園等でそれぞれ異なる以下の料金については、無償化の対象外となっています。
- 通園送迎費
- 行事費
- 食材費(主食費と副食費)
- 行事費
- 施設費など
ここで注目したいのが、パンやごはんなどの「主食費」と、おかずやオヤツといった「副食費」で構成させる「食材費」です。
食材費は、以前は施設を利用する「認定号数」によって実費負担額が異なるものでした。
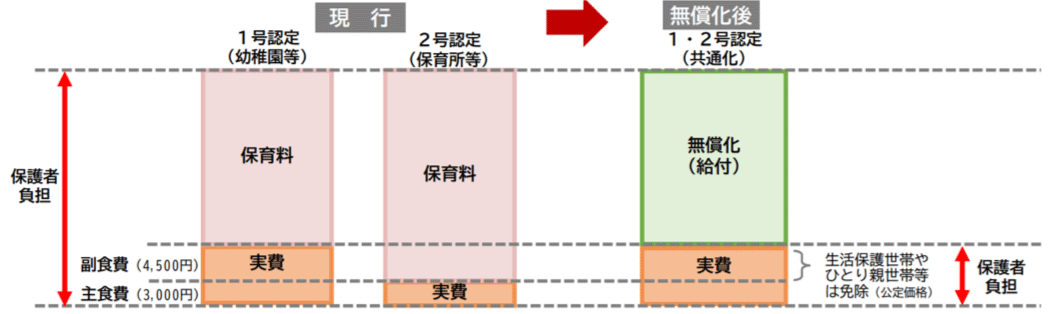
出典:内閣府「公定価格の対応の方向性について」
上記の図の通り、2号認定の家庭は、無償化後は主食費に加え「副食費」を実費で負担することになります。
このため「保育料の無償化によって給食費が上がった…」という声が上がっているのです。
保育の認定基準
子どもを地域の保育施設に預けるには、市町村から保育認定を受ける必要があります。
子どもの年齢や保育施設の利用理由により、保育施設や利用可能な時間が決定することになります。
| 子どもの年齢 | 保育を必要とする事由 | 利用できる施設 | |
|---|---|---|---|
| 1号 | 3~5歳 | なし | 幼稚園・認定こども円 |
| 2号 | 3~5歳 | あり | 保育所・認定こども園 |
| 3号 | 0~2歳 | あり | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
| 認定の必要なし | 0~2歳 | なし | 必要に応じて一時預かり等利用可能 |
1号・2号認定の給食費負担額の差
2号・3号の認定にまつわる「保育を必要とする事由」とは、
- 就労(フルタイム・パート・居宅内労働等)
- 妊娠・出産
- 保護者自身の疾病や親族の介護・監護
上記のような、家庭内での保育が不可能な状況を指します。
また、保護者の状況に応じ、最長8時間の「保育短時間」から最長11時間の「保育標準時間」まで、預かる時間も決定されることになります。
以前から、1号認定と2号認定の間での給食費の負担額の差は、公平性が問題視される点のひとつでした。
今回の新制度では、保育料を無償化すると同時に、給食費も実費に統一されたことになります。
3号認定の給食費はどうなる?
保育料無償化に伴って給食費が上がることになる2号認定は、3~5歳児の子どもが対象となります。
では、3号認定である0~2歳の子どもを預けている場合にはどうなるのか気になりますよね。
新制度「幼児教育・保育の無償化」では、0~2歳児の保育料無償化の対象は「住民税非課税世帯」に限られています。
また、0~2歳児にあたっては、副食費と主食費は以前より保育料に含められています。
無償化でもその制度が移行されるため、非課税世帯であるなしに関わらず、3号認定の給食費が実費で新たに必要となるということはありません。
スポンサーリンク
シングルマザーの子どもの給食費はいくら?

新制度以前より、ひとり親家庭の副食費の実費負担は、公定価格である4,500円まで免除されています。
その他、年収360万円未満相当世帯・全世帯の第3子以降についても副食費は免除とされ、新制度でも支援は継続されています。
しかし、一般社団法人ひとり親支援協会のアンケートによると、ひとり親家庭の18.8%が今回の新制度で「負担額が増えた」と応えています。
出典:一般社団法人ひとり親支援協会
保育料が軽減されるはずの無償化制度で、なぜ保育料にかかる費用負担額が増加するという「逆転現象」が起こってしまうのでしょうか?
これまで「主食費」を徴収していなかった保育所の場合
食材費には主食費(パン・ごはん)と、副食費(おかず・おやつなど)が含まれています。
主食費は以前より実費負担が基本でしたが、一部では主食費は徴収しない方針を取る保育所も見受けられました。
今回の無償化で、食材費を一律にするため主食費が徴収された場合、今まで保育料が無料や低額であった低所得世帯ほど、給食費の負担額は増加することになります。
設備費や行事費、送迎バスや延長保育料などの値上げ
新制度に伴い、設備を拡大した保育所や幼稚園では「施設充実費」等の設備費が増額されています。
その他、保育料の無償化を機に行事費や延長保育料が改訂されるケースもあり、低所得世帯の負担増加へと繋がっています。
まとめ|保育無償化でも3~5歳児は給食費が必要
以前より、認定号数によって負担金額の開きがあった給食費。
今回の幼児教育無償化を機に給食費について統一化が図られ、結果、2号認定の子どもについては副食費の実費負担が必要となりました。
その一方で、食育のひとつである給食の費用が実費負担であることを、問題視する声も上がっています。
また、副食費の追加に加え、必要経費が値上げ等は低所得世帯であるほど負担が増加することになります。
保育の無償化によって多くの家庭で保育料が軽減されてはいますが、待機児童や保育士の雇用といった、保育の受け皿に対する問題は未だ山積みとなっています。
幼児期から大学進学に至るまでの教育格差を広げないためにも、ひとり親家庭をはじめとする各世帯への子育て支援は、まだまだ検討する余地があると言えるでしょう。
 教育費の大学無償化!低所得シングルマザーに「大学等修学支援法」を解説
教育費の大学無償化!低所得シングルマザーに「大学等修学支援法」を解説 

